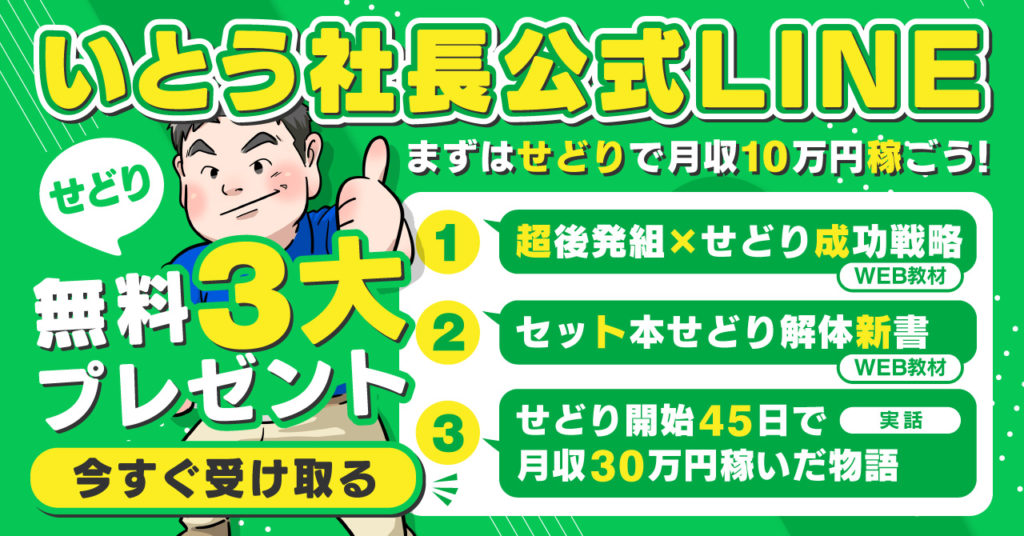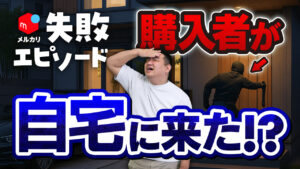こんにちは!伊藤(@hirokazuito0821)です。
今回は私自身が運営する古着卸の立場から、2025年において「古着の店舗せどり」が現実的に稼げるのかを徹底検証しました。
タイトル通り、6時間ほぼガチで店舗を回ってリサーチをしてみた結果を率直にまとめます!
検証の目的と背景
まず、私は古着卸と古着販売の両方を見ている立場です。自社での仕入れライン(1着250円で仕入れられる仕組み)や販売データに日々触れているため、相場感は持っています。
それでも視聴者さんから「卸も使いたいけど店舗ってどうなの?」という問い合わせを大量にいただいていて、実際にユーザー目線で検証してほしいという声が多かったため、今回自分の足で回って確認することにしました。
当日の行動スケジュール(6時間の流れ)
当日の流れはざっくり以下の通りでした。
- 1店舗目:セカンドストリート(リサーチ)
- 2店舗目:ブックオフスーパーバザー系(リサーチ)
- ランチ休憩:名古屋・緑区の有名ラーメン店でランチ
- 3〜4店舗目:再度セカストなどを巡回(リサーチ)
- 検証終了、所感まとめ
車で移動しながら、駐車場の空きや店舗の混雑、陳列の状況、価格帯、見つけやすさなどを丁寧にチェックしました。以下、各店での具体的な発見と私の率直な感想を時間軸に沿って書きます。
1店舗目:セカンドストリート到着

到着してまず思ったのは「探すのが大変」でした。古着の陳列はブランドやカテゴリ、ランクで分かれているけど、店舗ごとに並べ方が違う。しかも、値段が高めに設定されていることがほとんどです。
例えば、あるワンピースが900円で売られていましたが、私の基準(自社卸で250円仕入れ→2500円売り想定)で考えると利益が出る商品でした。しかし店舗では同じアイテムが箱に詰まっていたり、タグ付けが高い価格設定になっていたりで、見た目だけでは一瞬で判断できないケースが非常に多いです。
店頭でよく見かけた問題点:
- 価格帯が高め(家賃・人件費反映)
- 目立つ利益商品はライバルが回収済み
- ブランド名や状態が把握しづらい陳列(箱入りや重なっている)
リサーチしていくと「これは取れそう」と思えた商品でも、値札を確認すると4,200円や5,000円といった販売価格が付いており、利益シミュレーションが合いませんでした。
価格の実例と感想

動画中でのやり取りを思い出すだけでも、以下のような具体例がありました。
- 900円のアイテム → 自社基準だと利益出るが店舗だと厳しい
- 4,200円のコート → 一見「高値」だが、仕入れ値を考えると初心者には手が出ない
- 1,760円のアイテム → メルカリの相場を考えると微妙
結論としては「店舗の売価が高すぎて、初心者が利益を出すのは難しい」。これが1店舗目の正直な感想です。
2店舗目:ブックオフスーパーバザー
ブックオフスーパーバザーなどの大型リユースチェーンでも同じく課題がありました。雑貨や家電のように明確な型番で判断できる商品と違い、洋服は見極めに時間がかかります。ブランド名がタグにない、予測変換でも出ない古いブランド、状態の判断が人によってブレる……こうした要素が初心者にとってのハードルです。
さらに、顔や年齢、体格によって店員さんや他のお客さんからの視線が変わる場面があるのも事実。若くて見た目が良い人がリサーチをしていても気になりませんが、我々のように年齢が上の男性が来ると明らかに煙たがられます。店舗という「公共の場」での仕入れは心理的負担もあるのです。
ランチ休憩

店舗巡りの合間に、名古屋の緑区で有名な家系ラーメン店に寄りました。こういう“楽しみ”がないとやってられない、というのは本音です。長時間のリサーチは体力的にも精神的にも消耗します。
この休憩時間に感じたのは、「店舗せどりは一種の体力勝負」だということ。駐車場探し、店内ウロウロ、レジの列、移動時間。これらはすべて“コスト”です。
3店舗目以降と長時間のリサーチの現実
今回、合計で約6時間を店舗巡回に費やしました。棚やハンガーをじっくり見れば確かに掘り出し物が出てくることもありますが、見つけたところで利益が数百円〜数千円程度。そこにかかる時間と移動コスト、ガソリン代、そして消耗を考えると効率が悪いとしか言えません。
時間がかかる理由:
- 行き来の移動(渋滞や駐車場待ち)
- 商品を1点ずつ確認する手間
- タグの読み取り・相場検索(スマホでの確認)にかかる時間
- 他のせどらーがすでに利益商品を回収している
正直に言うと、同じ時間を家で仕入れ作業(オンライン購入や卸仕入れの確認)に充てた方が、時間効率が良いです。
雑貨と洋服の違い
中古の雑貨や家電であれば、バーコードを読み取ると一発で相場が分かることが多く、店舗でも比較的すばやくリサーチができます。しかし洋服は型番が無く、ブランド名も多岐に渡り、状態評価が主観的。これが店舗せどりを難しくする最大の理由の一つです。
地方の店舗はそもそも回りに購入層が限られているため、値付けが変わりやすいという問題もあります。
発見の少なさとライバルの存在

店舗せどりを困難にしているのは「他のライバルが既に利益商品を取っている」こと。SNSやYouTubeで発信している人が多いので、利益商品は速攻で消えるケースが目立ちます。視聴者さんが同じ情報を見て稼ごうとすると、相当な頻度で店舗を回らないといけません。
これが「初心者は店舗に行くべきではない」と私が強く主張する最大の理由です。相場感がない状態で疲れて店舗を回っても、時間だけが消費され、結果的に稼げないまま終わる可能性が高いのです。
店舗せどりの精神的・物理的デメリット

ここまでの体験を整理すると、店舗せどり(店頭仕入れ)には次のようなデメリットがあります。
- 時間コストが非常に高い(移動・駐車・会計など)
- ガソリン代や高速代などの交通費が発生
- 商品の見つけにくさ(陳列やタグ付けの問題)
- ライバルによる先取りで利益商品が残らない
- 心理的ストレス(視線、店員対応、クレームの可能性)
- 季節・地域差により不安定
正直に言えば、「趣味でやる」なら楽しいですが、副業や本業として継続して利益を求めるなら効率が悪すぎる、という結論に至りました。
それでも店舗せどりをやる場合の“現実的”な改善ポイント
店舗せどりを完全に否定しているわけではありません。もしやるなら、以下のポイントを徹底してください。
1) 相場感の徹底
どのブランドがいくらで売れているか、最低限の相場をスマホで即判断できるレベルにする。相場が分からない状態で店舗に行くのは時間の無駄です。
2) 戦略的に店舗を選ぶ
大手チェーンだけでなく、地域の小さなリサイクル店を狙う。地元の個人店は意外と穴場があります。
3) 動線と時間管理を最適化する
駐車場の位置、店内の導線、会計待ち対策を考える。1店舗に長居しない。短時間で判断できるスキルを磨く。
4) 見た目より“数字”で判断する癖をつける
「これ良さそう」という感覚ではなく、過去の売れ行きや実際の販売相場をベースに仕入れる。感情はなるべく排除。
5) 法的・モラル面の注意
店舗での大量仕入れや特定商品の買い占めは店舗の迷惑となる場合がある。地域の店舗と良好な関係を築くことも重要です。
代替案:卸を活用するメリット
私が強く勧めるのは「店舗せどりから卸仕入れに乗り換えること」です。理由は簡単で、時間効率・コスト効率が桁違いに良いからです。
- 在庫は事前にピックされて届くため、探す時間が不要
- 仕入れ価格が安定(例:1着250円〜)
- 発送やサポートがあれば初心者でも売り切れるまでフォローが受けられる
- 移動コストゼロ(自宅で仕入れ・出品が可能)
実際に私たちの卸では、古着卸を審査制で運営することで品質の担保と流通管理を行っています。者に向けた具体的アドバイス(やるならコレだけ守れ)
結論:2025年、店舗せどりで継続的に稼ぐのは「難しい」
今回6時間ガチで回って得た結論を一言で言うと「無理です」。もちろん例外はあります。例えば地域差で相場が安い場所に住んでいる、洋服の目利きに長けている、行動時間を多く確保できる人であれば稼げる可能性はゼロではありません。
ただし一般的な初心者や副業レベルで「YouTubeで見た情報だけで店舗に行けば稼げる」と思っている人は、現実を直視した方が良いです。時間と体力を消耗して終わるリスクが高いです。
おわりに
今回の検証は6時間という短い時間ながら、店舗せどりの厳しい現実をかなり明確に示す結果となりました。古着物販で稼ぐこと自体は可能ですが、方法は多様です。店舗での“掘り出し”が好きなら楽しんで続ければいい。でも「時間をお金に換える」ことを重視するなら、より効率的な仕入れ方法(卸やオンライン)を選ぶべきです。
もしこの記事を読んで「卸に興味がある」「効率的に稼げる方法を教えてほしい」と思ったら、この記事の下にある公式LINEに登録して、古着卸の説明会を受けてみてください!
迷っている方向けに、1000〜3000円利益の出る古着の特別プレゼント企画も行っています。数に限りがあるので気になった方はお早めにどうぞ!
=======
この記事を動画で見たい人はこちら