Warning: Undefined variable $kanren in /home/kazdon/kazdon.jp/public_html/wp-content/themes/swell_child/functions.php on line 587
こんにちは、伊藤(@hirokazuito0821)です。
近年「副業OK」という会社も増え、会社勤めの傍らに副業でプラスアルファの収入を得ている方も多いことでしょう。そこで気になるのが副業収入の確定申告についてですよね。
会社員の方の多くは、医療費控除や住宅ローン減税、ふるさと納税などの寄付金控除がない限り、所得税の確定申告をしたことがないと思います。
確定申告とは、1年間の所得を計算して税務署に申告し、納税することをいいます。収入のあるところには必ず税の申告がついて回るものですが、副業の場合の申告はどうなるのでしょうか。
今回は副業での確定申告の方法、申告する際のポイントなどを詳しく解説していきます。このページをお読みいただき、確定申告の仕組みについてしっかりと理解してみなさんの副業ライフを充実させましょう!
副業で得たお金は確定申告が必要?

ズバリ結論から申しますと、副業で得たお金の確定申告は必要です。
日本の税制は基本的に「申告納税制度」です。税金を納める側である国民が税制を正しく理解し、その上で自分の課税所得額を算出し、そこから支払うべき税額を算出して、自己申告の上で納税する形をとっています。
本業でも副業でも、何らかの収入があったのであればきちんと申告し、相当分の納税をしなければなりません。申告を怠ると罰則があるので注意しましょう。
ただし、副業の収入額や形態などの規模によって申告内容が変わったり、確定申告が不要になる場合があります。
副業で確定申告が必要な条件は?
本業が会社員の場合、原則として給与支払い時に源泉徴収をされているため、年末調整を受けていれば確定申告をする必要はありません。
副業で確定申告が必要になる条件は以下の②、③の場合です。
| ①給与年収が2,000万円を超える人 | 1年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、自身で確定申告が必要。 |
| ②副業の所得が20万円を超える人 | 本業以外の収入(副業の収入)が20万円を超える場合、雑所得として申告が必要。
ただし副業収入が給与の場合は「③2カ所以上から給与をもらっている人」となります。 |
| ③2カ所以上から給与をもらっている人 | 2カ所以上から給与をもらっていて、各会社で源泉徴収や年末調整をしても正しい納税額にならないので、確定申告が必要。 |
副業をしていても確定申告をしなくていい場合とは
逆に副業をしていても確定申告をしなくてもいい場合もあります。
副業の収入が本当に小遣い稼ぎ程度のものである場合は、その税額に対して確定申告の負担が大きくなってしまうこともあり得るため、確定申告をしなくても良いことになっています。
以下に詳しい条件を挙げます。
| A. 給与が1カ所の場合 | 副業の「所得金額」が20万円以下のとき |
| B. 給与が2カ所以上の場合 | 年末調整の対象外となる給与(副業)の「収入金額」及び、副業等で得た給与以外の「所得金額」の合計が20万円以下のとき |
「所得金額」は収入金額から必要経費を差し引いた利益・儲けのことで、「収入金額」は給与や売上など、支払いを受ける総額のことです。
二つは所得税の上では似ているようでまったく意味が違いますので注意してください。
なお、所得税の確定申告が不要な場合でも、市区町村へ住民税の申告が必要ですので気をつけてください。
また、副業の収入が20万円以下でも確定申告をした方が得するケースもありますので、ご自身の状況をふまえて検討し、一番良い方法を選んでください。
住民税の申告、20万以下の場合での確定申告をする場合の条件はこちらで詳しく紹介しています。
確定申告が必要なサラリーマンとは?
今まで書いてきた内容をふまえ、サラリーマンだけの方、副業収入が20万円に満たない方は確定申告をする必要はありません。会社で年末調整を受けていれば、原則として給与支払い時に源泉徴収をされているからで、勤務先が収入から税金を天引きし、年末調整で過不足の清算までしてくれています。
ではどんなサラリーマンが確定申告をする必要があるのか、以下に必要なケースをまとめます。
| ①給与年収が2,000万円を超える人 | 1年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、自身で確定申告が必要です。 |
| ②副業の所得が20万円を超える人 | 本業以外の収入(副業の収入)が20万円を超える場合、雑所得として申告する必要があります。
ただし副業収入が給与の場合は「③2カ所以上から給与をもらっている人」となります。 |
| ③2カ所以上から給与をもらっている人 | 2カ所以上から給与をもらっていて、各会社で源泉徴収や年末調整をしても正しい納税額にならないので、確定申告する必要があります。 |
| ④贈与を受けた人 | 親などから110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税の申告が必要です。 |
| ⑤マイホーム(不動産)を売却した人 | マイホームを売却して利益が出た人は確定申告をしなければなりません。
逆に売却をして損失が出た場合でも、確定申告をすることで給与など他の所得から控除(損益通算)できます。 |
| ⑥投資信託を売約した人、FXで利益が出た人 | 普通分配金が課税対象として扱われます。所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、地方税:5%が税率です。FXはここに復興特別所得税0.315%が追加されます |
副業で確定申告をしたお金が戻ってくる?
副業がアルバイトやパートであった場合、確定申告をきちんとしていると、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
この場合、通常毎月の給料からは、本業の給料よりも高い税率で所得税が天引きされるからです。
またアルバイト感覚の仕事でも契約方法が「委託契約」だった場合、その他フリーランス・個人事業の場合は、先に売上から源泉所得税が天引きされている場合があります。これは実は税金の前払いをしているような状態です。
そのため確定申告をすることにより、既に天引きされて支払い済みの源泉所得税が戻ってくる可能性があります。
副業での確定申告はどのように行うの?
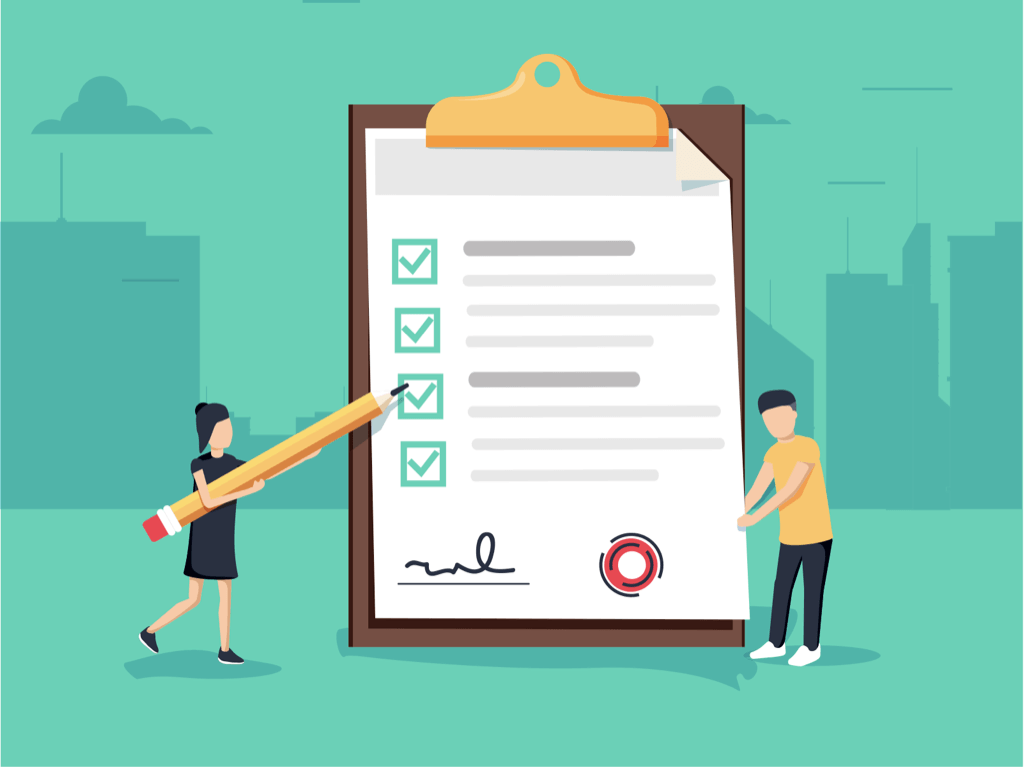
副業で得た所得を確認する
これまで紹介したように、副業の所得が20万円を超えている人は確定申告をする必要があります。実際どのように確定申告をするのかというと、一番最初にすることとしては、申告すべき所得を確認します。
所得には10種類あり、所得によって税金の計算方法が異なるため、まずはどの所得に当てはまるのか確認しましょう。
副収入については、年末から1月にかけて支払元の会社から、源泉徴収票や支払調書が送られてくることがあります。
これらの書類が送られてきた場合には、所得の区分がどのようになっているのかを確認してください。
給与所得の源泉徴収票が送られてきた場合
所得の区分は「給与所得」となるので、勤務先の給与と他の会社の給与を計算して、給与所得を計算し直す必要があります。
支払調書が送られてきた場合
所得の区分は「雑所得」となるので、収入を得るためにかかった必要経費を自分で計算し、雑所得を計算する必要があります。
経費を引く
確定申告すべき所得が確認できたら、その所得が「雑所得」であり20万円を超える場合、必要経費を差し引くことが認められます。
経費にいくら使っているのかを把握し最終的に計算するためには、帳簿をつけておく必要があります。
いざ確定申告をするとなったときに慌てなくていいように、領収書やレシートなどは適宜まとめ、普段からこまめに帳簿をつける癖をつけておくことをおすすめします。
必要経費の計算ができたら所得金額がいくらになるかを確認します。
所得税が課されるのは、収入から経費を差し引いた金額(所得=収入ー経費)です。
青色申告とは
税務署に所得と納税額を申告する確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」と呼ばれるふたつの方法があります。
青色申告の方が白色申告より複雑で難しいという印象が持たれがちですが、実はそれほど違いはありません。その上、青色申告をした方が得をすることが多く、最近は誰でも使える会計システムツールなども様々あり、計算などをしやすくなっているのでおすすめです。
青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。原則、複式簿記というやや複雑な方法を利用して帳簿を記録するため、その分手間がかかります。
手間がかかる代わりに特典が用意されており、事業の儲けから最大65万円(もしくは55万円)を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる制度があります。
白色申告と比較して節税効果の高い申告制度だと言えるでしょう。なお、税務署に事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。
以前は白色申告のメリットとして帳簿の記帳義務がないということがありましたが、2014年(平成26年)分からは、全ての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(5~7年)」が義務付けられたため、このメリットはなくなりました。
白色申告の方が気軽にできるように思われるかもしれませんが、10万円の特別控除が認められる青色申告と作業内容や作成書類などの手間はさほど変わらないため、よほどの事情がない限りは青色申告を選択することをおすすめします。
所得額における税率と計算とは
副業を含む所得は、合計の所得に対して課税されます。
事業所得や給与所得、雑所得等は総合課税とされるため、全ての所得の合計金額から所得控除の合計額を差し引いた金額(課税される所得金額)に応じて、5~45%の税率が課されます。
さらに、平成25年から平成29年までは、その年分の基準所得額の2.1%を復興特別所得税として、併せて申告・納税することになっています。
給与所得で年末調整をしている場合、課税される所得税額から既に納付済みの所得税を差し引いた金額を確定申告で納付することになります。
以下、平成27年以降の所得税の税率表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
副業で得たお金ごとの確定申告のポイント

副業で得た収入は所得の区分ごとに異なる確定申告のポイントがあります。それぞれ見ていきましょう。
事業所得の場合
副業の内容として最も業種が多岐にわたり、必要経費の幅も大きいのが事業所得です。
アフィリエイトやオークションなどは支払い明細や取引履歴をもとに収入の漏れがないように気をつけましょう。
なお、オークションやフリーマーケットで、自分の生活で使用しているもの(1組30万円以上の貴金属等を除く)を売却する場合は非課税のため、計算に入れなくても大丈夫です。
ライターやカメラマンなど源泉徴収の対象となる報酬を受け取る場合には、支払調書だけに頼るのはやめましょう。
差し引くことができる必要経費は、自宅で業務を行う場合の家事関連費はもちろんのこと、取引の相手先に行くための交通費や打合せ・接待などの飲食代なども入ってきます。
領収書を必ずもらうようにし、誰と何のために使用したのかなどのメモも併せて残しておくと良いでしょう。
月別、用途別などに分けておいたり、忙しくてもこまめにまとめておくと後々焦らずに確定申告の準備ができるのでおすすめです。
不動産の場合
不動産所得がある人というのは、賃貸経営をしていたり、投資用マンションなどを購入して会社勤めをしながら大家をしていたりする場合です。
収入には、毎月の家賃はもちろんのこと、礼金や更新料など、不動産を貸し付けることで受け取る対価が含まれます。
必要経費に含まれるものとしては、建物部分の減価償却費や固定資産税、管理費、借入金の利息などが挙げられます。さらに不動産所得は、事業的規模で貸し付けを行っているかどうかで扱いが変わってくるのが特徴で、事業的規模かどうかということは個別に判断されます。
漏れないように注意して計算し、計上しましょう。
株式投資
上場株式等への投資で得た利益は、原則として確定申告が必要です。
しかし特定口座で源泉徴収ありの場合はそこで課税が終了し、NISA口座で非課税期間内の場合は課税されないため、確定申告は不要です。
特定口座では年間取引報告書が発行されますが、一般口座の場合は自分で売買報告書などから所得を計算する必要があります。
また特定口座で源泉徴収ありの場合でも、複数の口座で赤字・黒字があるときは確定申告をすることで口座間の相殺をすることができます。
取引状況や口座区分によって確定申告が異なるため、確認の上、申告をしましょう。
雑所得の場合
雑所得は収入金額から必要経費を差し引いて所得額を出すというシンプルなものです。
所得金額に対して税率をかけ、控除額を差し引いて税額を算出します。1年間の雑所得の金額が20万円を超えると雑所得も確定申告が必要です。
FX取引や仮想通貨の場合の収入金額は、FX会社の「期間損益報告書」などから年間損益とスワップポイントの合計額を集計します。
必要経費としては、取引手数料やFX取引で使用する機材、インターネット代、書籍代などが計上できます。
副業での確定申告に関するまとめ

一口に「副業」と言えど、片手間程度に気軽に行っているものから、毎日それなりに時間をかけて真剣に取り組んでいるものまで幅があり、その収入額も人によって大きな差があることでしょう。
基本的に副業での収入が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、控除などが受けられメリットが多いことから、青色申告をする方がおすすめです。
近頃は初めての人でも比較的簡単に帳簿をつけたり書類を作成したりできる会計ソフトや確定申告ソフトなども豊富にあるため、それらを活用してみるのも良いでしょう。
わからないところは税務署でも詳しく教えてもらえます。
実際に確定申告をする際は副業の種類によって申告方法や内容などに異なる点があるため、自身の副業とそれにかかる必要経費などを把握し、この記事に記載した内容も参考にして申告をしていただけると幸いです
ではまた!
もう…店舗せどりやめませんか?
自宅に利益商品が届くので、あとは売るだけ!
「いとう社長卸サービス」を使えばわざわざ店舗に仕入れに行く必要はありません。
詳細は以下のLINE登録すると案内が流れます!
いとう社長卸の詳細はこちらから
↓↓↓

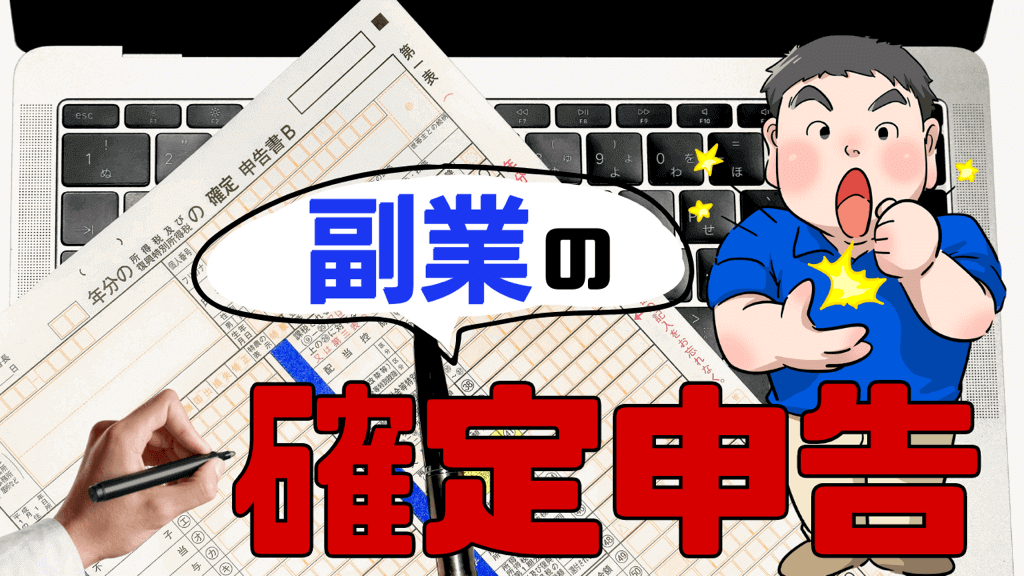
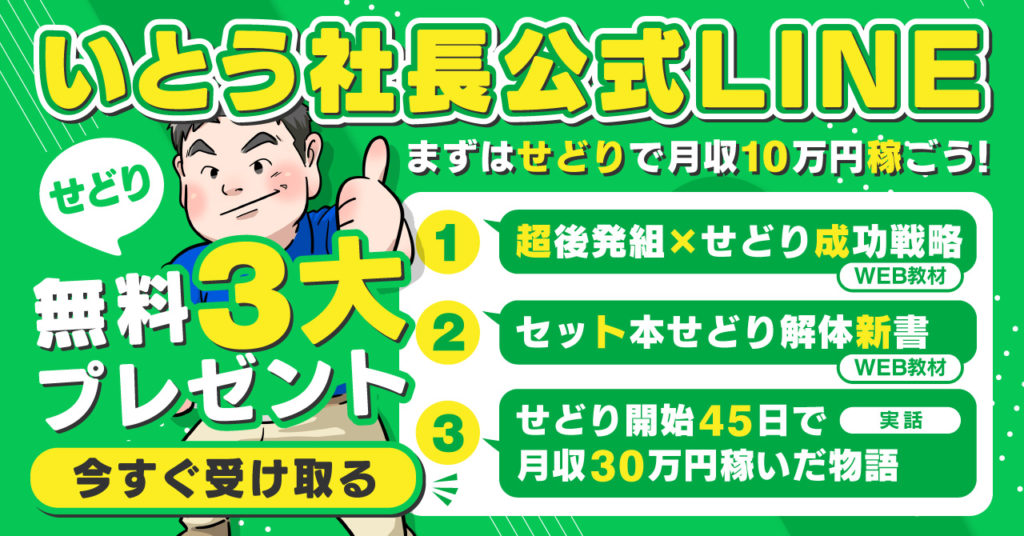

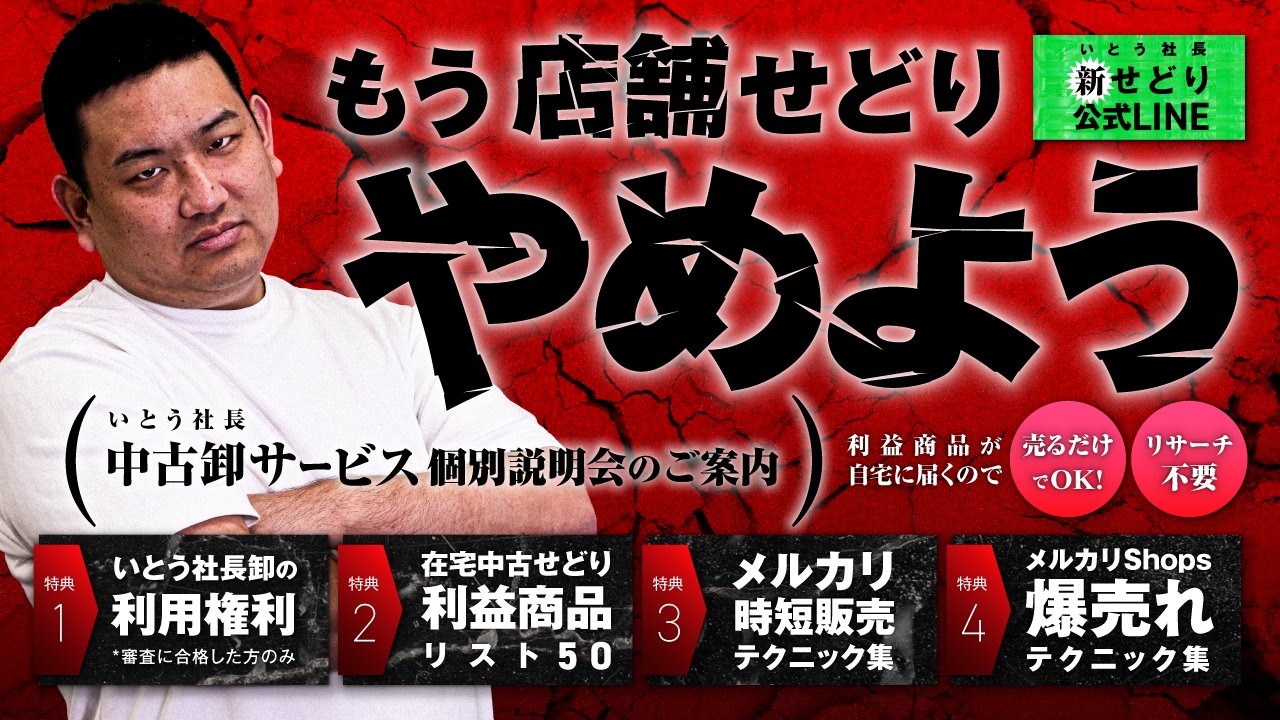







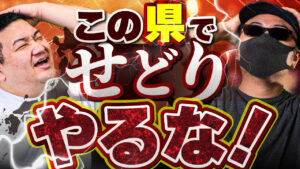
コメント